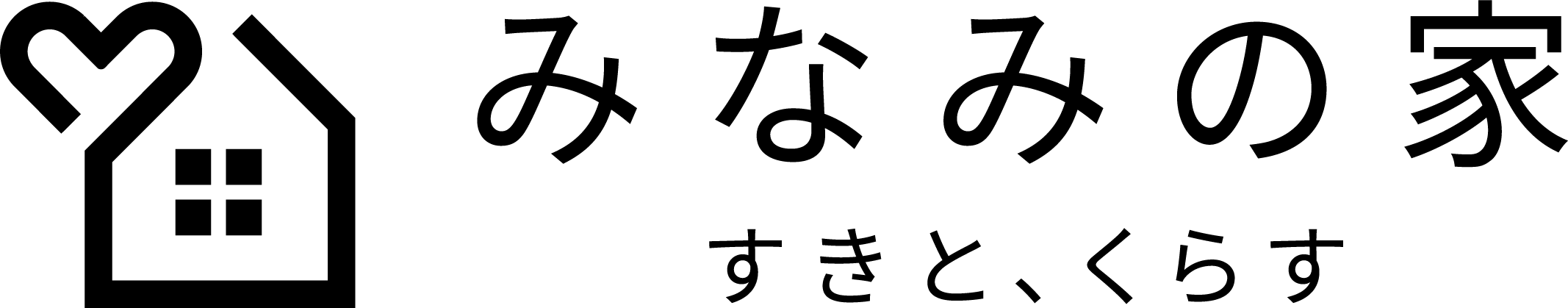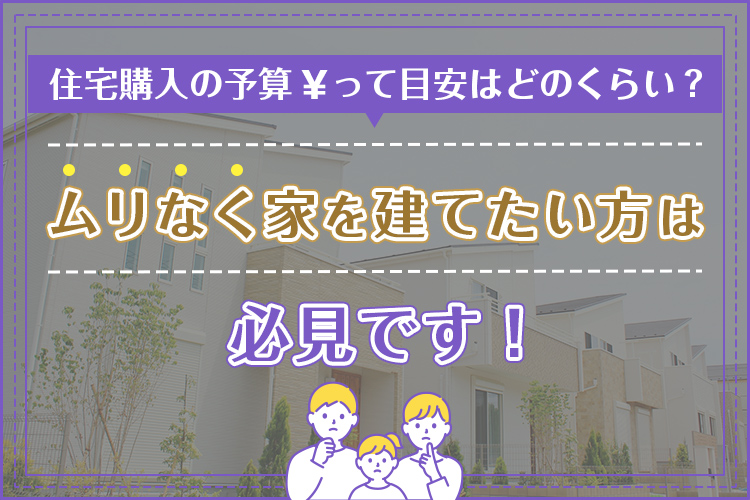地震に強い家をつくるには?新築でできる『備え』の工夫いろいろ

目次
地震に強い家をつくるには?
新築でできる『備え』の工夫いろいろ
2025年7月、トカラ列島近海で最大震度4の地震が発生しました。鹿児島では比較的地震が少ないと言われていますが、ここ最近の揺れをきっかけに「家の備え」について考える方が増えています。
新築だからこそ、地震に強い家づくりはしっかり検討したいポイントです。今回は、安心して長く暮らすために、家を建てるときに取り入れたい地震対策をご紹介します。
1. ハザードマップを活用しよう
まずは、土地選びの段階で地震や津波・液状化などのリスクを確認しましょう。
- 自治体のハザードマップで、地盤や浸水想定区域を確認
- 地盤調査を事前に実施して、安全性を把握
- 過去の災害履歴や周辺環境も考慮
2. 耐震等級をチェック!
建物の「耐震等級」は、家の揺れへの強さを示す指標です。
- 等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能
- 等級2:等級1の1.25倍の耐震性能(学校や避難所レベル)
- 等級3:等級1の1.5倍の耐震性能(消防署や警察署レベル)
南日本ハウスでは、長く安心して暮らせる家づくりのために、耐震等級3相当の構造にも対応可能です。
3. 家具の転倒防止や収納設計
建物が倒壊しなくても、家具の転倒は大きなケガや避難の妨げになります。
- 造作家具で転倒しにくい設計に
- 重いものは低い位置に収納する
- 寝室には大きな家具を置かない・倒れない工夫を
4. 非常用の備えも忘れずに
災害時に自宅避難を前提とした備蓄スペースも大切です。
- ペットボトルの水、非常食、トイレセットなどを常備
- ガス・電気が止まったときのためのコンロやライト
- 家族全員の分の非常用品を入れる収納の確保
5. 太陽光発電や蓄電池の活用
電気が止まったときに、太陽光や蓄電池があると安心。
災害時でもスマホの充電や照明の確保ができると、情報収集や安全確保に役立ちます。
まとめ
災害は「いつか」ではなく「いつ起きてもおかしくない」時代。新築のタイミングこそ、暮らしを守る備えをしっかり考えるチャンスです。
南日本ハウスでは、土地探しの段階からハザードマップを踏まえたご提案、耐震設計や収納計画、さらには太陽光・蓄電設備までトータルでご相談いただけます。
安心・安全な家づくりを、一緒に考えていきましょう。